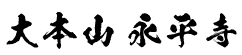禅の里永平寺だより
永平寺と栢樹庵 ~栢樹庵再建に因んで~
大本山永平寺
監院 小林昌道
元号も平成から令和と改まった本年七月二十三日、永平寺門前の一院である栢樹庵の再建が成りました。
その始めは、享保初年(1716)頃江戸高輪泉岳寺に縁故を持つ本山三十九世承天則地禅師を開山、その法嗣である貞實尼を庵主として大工村に草創され、本山に随喜する尼僧の宿泊、安下処として発祥したものと想定されます。開基は、玄源左衛門と伝えられています。
その玄家が文政十(1827)年、大工村より門前に屋敷替えをすることになり、柏樹庵も現在の地に再建されました。これは、二年後の二代尊五五〇回大遠忌を目前にしてのことで、柏樹庵の再建によりこの大遠忌には、尼僧の随喜衆が700人に及んだとの記録があります。
戸籍制度が始まった明治五(1872)年の『本山明細帳』によれば、永平寺には長寿院、嶺梅院、隆昌院、地蔵院の四つの塔頭寺院と永平寺庵室として柏樹庵が記載され、柏樹庵には、住尼・恵運と8名の尼僧が住居しています。
近世以降の柏樹庵は、本山拝登尼僧の旦過としての役割を担いつつも、尼学林として尼僧が住居して門前衆信徒と交流を持ちながら本山行持や運営に関わってきました。
再再建にあたり
今回の再建にあたり、寺号「柏樹庵」の名前は「栢樹庵」となりました。これは、現在本山法堂で講式に使用する小鏧子は栢樹庵貞實尼の寄進によるものであり、その小鏧子には「柏」の文字が「栢」と刻字されていること、並びに柏樹庵の歴史を引き継ぎながらも再再建により新たな歴史を為していくためであります。
現在、高祖大師のみ教えは世界に広まっており内外を問わず道を求める方々が永平寺に拝登されております。
このことに鑑み、眼蔵会、高祖大師報恩授戒会、御征忌、摂心会等の永平寺の行持に希望される女性修行者の宿泊、安下処として「栢樹庵」の役割を復活させることこそが急務でありました。
再再建が成り、新たな時代に新生「栢樹庵」として永平寺と共に歴史を歩んでいくことを願いご挨拶申し上げます。

在りし日の様子(2013年)