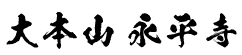永平寺の御開山道元禅師(どうげんぜんじ)さまは、鎌倉時代(一二〇〇年)に、京都でお生まれになりました。
道元さまは、八歳の冬に母を亡くされ、その際の香の煙を観て、無常を観じ、出家を決意したといわれます。
そして、十二歳の春に出家し比叡山にて修行をされ、沢山の経典を紐解き学ばれます。
道元禅師 略歴

道元禅師(1200年~1253年)
クリック(タップ)すると開きます。
仏道を求め修行に励む道元さまは、ある時「宋の国に、お釈迦さまの坐禅を正しく伝える禅の教えがあるから、宋に渡って道を求めてはどうか」と助言をいただきます。
そして、先に禅の教えを宋で学んでこられた栄西(えいさい)禅師の弟子である明全(みょうぜん)和尚と共に、宋の国に渡ります。
道元さまは宋国に到着早々、阿育王山の典座(寺の台所の責任者)と出会います。そして、彼と問答をする中で「あなたはまだ修行や経の文字とは何かわかってないな」と言われます。
後に道元さまが、老僧と再会し、問答をします。
「修行とは何ですか?」の問いに、「目の前にあるじゃないか!あなたの生活そのものだ。(遍界(へんかい)かつて蔵(かく)さず)」と。
また、「文字とは何ですか?」の問いには、「経文はただの文字だが、行ずれば仏だ(一、二、三、四、五)」と、いわれます。
私たちは元々さとりをそなえていても、修行しなければおさとりは現れないのです。つまり、修行とおさとりは切り離せない、同時にしかありえない一枚のもの(修証不二(しゅしょうふに))だったのです。
道元さまは宋国のお寺を巡る中で、ついに正師となる如浄(にょじょう)禅師と出会います。如浄禅師は、改まった作法や時候を気にせずに、いつでも質問をしに来るよう道元さまを肯います。
道元さまは、真に仏法を求め、様々な質問をぶつけました。そして、そのたびに如浄禅師は懇切丁寧に道元さまを導きました。
ある日、道元さまは他の修行僧と共に坐禅をしていました。その中で、一人の僧が居眠りを始めました。すると、如浄禅師は「坐禅は、身心脱落でなければならん!居眠りなどしていてはいかん!」 と温かくも厳しく修行僧を励まします。
坐禅の後、道元さまは如浄禅師のもとをたずね、感慨を述べ、如浄禅師に伝わる仏法をつぐことを許されました。
道元さまは、法をつがれた後も怠ることなく修行につとめました。おさとりの上にも不断の修行はつづくのです。
道元さまが日本に帰って初めて記されたのが「普勧坐禅儀(ふかんざぜんぎ)」です。それまでの、日本の坐禅のあり方や、作法などを正し、お釈迦さまから代々伝わる正伝の坐禅を示されたのです。
のちには、京都の深草に興聖寺を開創し、「正法眼蔵(しょうぼうげんぞう)『現成公案(げんじょうこうあん)』」
や「典座教訓」など、多くのみ教えを後世に残されました。
時が過ぎ、道元さまが四十三歳の頃、俗弟子であった波多野義重公の招きにより、越前の地に赴きます。
翌年、道元さまは大仏寺を開き、二年後に「永平寺」と改称します。永平寺では、如浄禅師の教えに従い、たとえ一人でも、正しいみ仏の教えを伝え行ずる者を育てようと身心を尽くされました。
道元さまが永平寺を開かれて約十年が過ぎようとした頃、患っていた病が重くなり、京都の俗弟子の邸にて治療に専念します。しかし薬石功なく、お亡くなりになられます。道元さまは満五十三歳でした。
永平寺では、今も150名近くの修行僧がみ教えに身を投げ入れ、日々修行をしております。