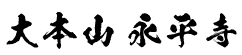禅の里永平寺だより
栢樹庵の落慶と柏樹関の竣工を迎えて
7月23日、栢樹庵の落慶と柏樹関の竣工を迎えることが出来ました。これに際し、記念誌を上梓いたしましたので、今回はその中から一部抜粋したものを掲載したいと思います。
① 栢樹庵について
栢樹庵は、尼僧衆が法要などで本山に拝登する際の、安下処・滞在所としての役割を果たしてきたお寺です。本山三十九世承天則地禅師(在任一七一六〜一七二九)を開山とし、その法嗣の貞実尼以来、ごく近年まで尼僧が代々その住職をつとめてきました。開基家は門前大工の祖、玄源左エ門家です。
当初、栢樹庵は門前大工村にありましたが、手狭になったため、文政十二年(一八二九)の二祖懐奘禅師五百五十回大遠忌の際に現在地に移転再建されました。本山の記録を見ると、この大遠忌では七百名の尼僧が上山したとあり、また、明治十一年(一八七八)の二祖六百回大遠忌の到着名簿にも三百九名の尼僧の名が記録されています。その後明治三十五年(一九〇二)の道元禅師六五〇回大遠忌前に再び改築されました。
常時は、住職とその弟子の尼僧が修行し、昼間は本山の庫院などにつとめておられました。嘉永五年(一八五二)の記録には住職恵心ら九名、明治五年の記録にも住職恵運ら七名の名が見えます。
このたび、禅の里事業の中で、栢樹庵はその佇まいを一新し、新しい時代の中で、歴史を継承しつつまた新たな役割を担っていくことになります。

落慶を迎えた栢樹庵

見守り続けるご本尊さま
② 柏樹関について
柏樹関は、福井県、永平寺町、大本山永平寺の三者が協力・連携して進める「永平寺門前の再構築プロジェクト」の一環で、禅の根本道場である永平寺の門前に建設された宿泊施設です。
建設の際には、本山と一般社会の中間地帯にあって一般参拝者や観光客が禅の心に触れることが出来る、永平寺境域に相応しい建築が求められました。
敷地は、深山幽谷の豊かな自然に恵まれた永平寺の門前に位置し、参道に沿って流れる永平寺川と山に挟まれた細長い土地が上流から下流に向けて緩やかに傾斜しています。そのため、建物は敷地の高低差を利用した断面構成としつつ、周囲の環境に馴染むよう雁行・分節して全体のボリュームを抑えました。また永平寺川と山並みを借景して、建物にも自然を取り込み、自然と建築の調和を図りました。
地域特性を最大限に活かした「親禅の宿」のコンセプトのもと、伝統美の継承、禅の空間、陰翳礼賛、地産地消というキーワードで展開しながら設計を進め、永平寺参道の賑わいの創出と、地方活性を目指しました。

柏樹関玄関棟