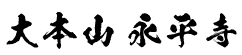永平寺が目指す「修行」とは、道元禅師の禅風を身に付けた人材の育成です。永平寺の修行について、よく「七百八十年変わらぬ‥」と言いますが、厳密には時の変遷と共に様々な変化がありました。
今、「修行道場の継承」と申しますのは、変わってはならないものは何か、時代即応的に変わらなければならないものは何か、この二つの命題を明らかにし、時代に応じて世に確かな法灯を掲げうる人材を養成し続けることであります。
かつて出家の意味は「出世間」であり、正に親を捨て親族知己とも縁を断って修行者となりました。しかし、現代は一定年数修行すると、育てられた寺に戻り住職になるべく歩み出すのが一般的です。
永平寺は、厳しい修行道場でありながら、大事な寺院継承者を預かってもいるのです。修行期間が短期化する中、お釈迦さまのお覚りを継承される道元禅師さまの「正伝の仏法」を修行僧に伝えることは容易ではありません。
高度経済成長期から平成の始めにかけて、永平寺には大挙して参籠参拝・観光の人々が押し寄せ、修行僧もその対応に追われたものです。しかし今はその数も当時の三分の一になっています。修行道場としては、道元禅師さまが示された本来の修行に立ち帰る好機と捉えています。
行住坐臥の四威儀、三時の勤行四時の坐禅を丹念につとめられるように指導して参ります。その上で、道元禅師さまの時代とは大きく変わった人心や世相に鑑み、修行僧一人一人が「行」と「学」を通して智慧と慈悲を身に付けた僧侶となれるよう適切な指導を心懸けて参ります。その方策の一つとして、既に山内役寮と山外有識者による「僧堂教育評議会」を設け、僧堂教育において伝統的なものを堅持しながらも時代相応の視点を加えるべく着手しております。
衆人が認めうる、確かな禅僧を育成することこそ、永平寺の「修行道場」たる所以(ゆえん)であります。
禅の里永平寺だより
「禅の里」事業とは
~永平寺の未来を見据えて~
永平寺は、平成二十五年より「禅の里」を構想し、現在その事業を推進しております。禅の里事業とは大本山永平寺が、
- 御開山道元禅師の御意志を継承する「修行道場」であること。
- 宗門檀信徒及び一般の方々が崇敬する禅の聖域として「不断の布教教化の場」であること。
- 聖域である深山幽谷の自然環境が護持され、かつ伽藍や境内地が安全で安心な修行・参詣の場であること。
これらの実現によって、百年・二百年後も世界に冠たる「禅の道場」であり続けることを、視野に入れた事業であります。
下記項目をクリック(タップ)すると開きます。
先に「修行道場」としての永平寺について申し上げましたが、お釈迦さま以来仏教は衆生済度を誓願として参りました。修行による自己変革と衆生済度は一つでなければなりません。
衣食住、物が無ければ人は生きて行けません。しかし、現代の人々は奔放な自我に振り回されて、いわば、物質文明の虜(とりこ)となり、真の依り所となる自己を見失い、迷い苦しんでいるのではないでしょうか。禅の道場である永平寺には、この迷いの中に在る人々を救う御開山さまの御教えがあります。「修行道場」として宗門僧侶を養成するばかりではなく、衆生済度、在家者化導の布教教化の道場でもあります。
仏教は「上求菩提教化衆生」と言い、自らの修行と人々の救済を一つのこととしてきました。一般の方々と関わり、語り合い、学ぶことで、自らの理解や修行を深めてきました。
永平寺は、出家修行者の道場でありますが、迷い苦しむ人々が道を求めて来ることを拒む所ではありません。私たちの目指す禅の里永平寺は、人々の心の依り所であり、万人の聖地であれと願っているのです。
そのために、参禅や参籠の研修などがあります。参禅は、三泊四日による本格的修行体験が可能な研修に加え、二泊や一泊の研修もあります。また、参籠については、吉祥閣でのこれまでの形に加え、永平寺が凖聖域として位置付ける伽藍から独立した寺域に、初心の方が無理なく修行道場の雰囲気に身を容れることが出来るよう、新たな宿泊施設を新設中です。
この施設は、ご高齢の方など、諸般の事情から永平寺内の厳格な規則に則(のっと)って起居することが困難な方も身を委ね、希望によって坐禅や法話に参加頂いたり、祠堂殿や法堂の御供養にお参り頂けるものとなります。
新たな宿泊施設とは、準聖域から無理なくお参り頂き、聖域永平寺とご縁を結んで頂くための施設であります。
永平寺を修行道場として、また、不断の布教教化の場として護ることが、今永平寺に在る者の責務であることは言うに及びません。
永平寺の永い歴史の中には、外護者の交替による衰微や、火災、あるいは台風等の自然災害など、幾度となく伽藍を失い、時には、暫く復興出来なかった事さえありました。伽藍消失と復興、それは永平寺が時代の中で存在を問われた歴史だったのかも知れません。そして、永平寺はその都度困難を乗り越えて参りました。それは時の禅師さまを中心に、道元禅師開闢の道場として思いを寄せる宗門寺院のお力と、御開山さまの祖廟である永平寺を尊崇する篤信の方々のご支援を受け、あたかも時代が永平寺を必要としているが如く、復興に次ぐ復興を果たしてきたのです。
この歴史を紐解く度に永平寺とその法灯を護持してくださった数多(あまた)の先人に対し、敬意と感謝の念が込み上げて参ります。そして、この法灯を未来永劫絶やしてはならないとの信念に至ります。
しかし、現代社会では古きものをそのまま遺すだけでは十分とされません。古の趣を慕いながらも、将来法灯を担うべき僧が日々の修行に精進し、永平寺を思慕尊崇する多くの参拝参籠者を受け入れるには、現在出来うる最上の方法を駆使し、安全で安心な環境を整えることが重要な課題となっております。
現在永平寺は、大小合わせて七十を超す伽藍や堂宇を有し、歴史上かつて無かった威容を呈しております。時代の趨勢に随ってのことでありましたが、現存の堂宇・伽藍の古きを保ちつつ、今日、法律や基準など様々な制約のなかでこれを護ってゆくことは容易なことではありません。
人と人とのつながり方が大きく変化し、全てが混沌の中に投げ込まれたような現代社会にあって、永平寺は人々の安寧の地でありたいと願っています。
これまでご縁を結んで下さった方は勿論、これから新たにご縁を結んでくださる方も、心のふる里・禅の里永平寺にご参拝頂き、真の拠り所となる自己を取り戻して頂ければ幸甚です。そして、その事が、聖域永平寺を護ることとなるのです。
お正月の正は、一に止まると書きます。「禅の里」は、原点の一を目指しています。
皆様のご理解をお願いいたします。